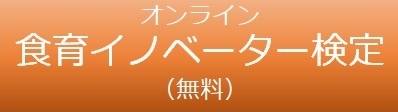今から10年ちょっと前、そのころ「食育ブーム」のようなものがありました。
きっかけは「食育基本法」という法律ができたこと。
この法律により、国および地方自治体それぞれが、毎年、食育のために予算を計上することが義務づけられました。
国の場合、その年間予算は関係省庁に振り分けられるのですが、
- 文部科学省:数億円
- 厚生労働省:10~30億円
- 農林水産省:100~150億円
といった予算構成になっています。
その結果、これからは食育だ!といった雰囲気が生まれました。
その影響で国や自治体だけでなく、多くの企業が「我が社も食育をしよう」といきりたち、食育の事業に手を出しました。
食業界の企業が食育に取り組むのは当然としても、食と関係のない企業もCSRの一環として食育に取り組みはじめました。
考えてみれば前述した食育の国家予算合計100~200億円が助成金の形で民間に来ると思えば、これが欲しいがために食育事業を始める民間企業もたくさんあったでしょう。
いわば猫も杓子も食育事業に参入してきた時代でした。
あれから10年以上がたちました。
どうなったでしょうか?
|
<目次>
|
1.食育ブームの「その後」
今では「食育」という言葉も一般化したように思われますが、その反面、「食育ブーム」自体はビジネスの世界では沈静化したように感じられます。
なぜ沈静化したかといえば、多くの企業が食育の事業化に失敗したからです。
食育の事業化に多くの企業が失敗した理由はとてもシンプルです。
それは、
- 同じような食育事業しか思いつかなかったから
- 国や自治体がやろうとしているのと似たようなことを民間企業がやろうとしたから
です。
食育というと、多くの人は「子どもに栄養教育を施すこと」といった印象を持ちます。
なので、食育の事業化を考える人たちも「子どもに栄養教育を施すことが食育である」という固定観念を持ち、そこから事業を発想しようとするので、似たような事業しか思いつかない。
他社も同じように子どもの栄養教育をしようとするので、どの会社の食育事業も似たり寄ったりになる。
また、国や自治体がやろうとしていることと似たようなことを企業がやろうとしても、うまくいくはずがありません。
なぜなら国や自治体が行う食育は、無償または安価で提供されています。
経済的に成立するようには考えられていないのです。
国や自治体が「ほぼ無料」で行っている食育活動と似たようなことを、企業が「それなりの価格」でやろうとしても、できるはずがありません。
食育を事業化しようとするなら、いわゆる典型的な「子どもの食育」については学校や幼稚園、食育団体などに任せ、自分たちはそれ以外の市場に進出すべきではないかと思われます。
2.食育の新しい市場の例:ビジネスマン
たとえば、「ビジネスマン」という市場。
日本で「ビジネスマン」というと「サラリーマン」とほぼ同義語になりますが、その数は約6千万人。
食育活動の対象と考えると「巨大な市場」です。
- 小学生の数が6百万人
- 専業主婦の数が7百万人
これらに比べても数字はケタ違いです。
サラリーマンの食生活といえば
- 昼はそのへんでラーメンをかきこみ
- 夜は残業やら接待やらで遅くまでお酒
といったイメージがあります。
筆者の知るかぎり昔のサラリーマンは本当にそんな感じでした。
今のサラリーマンは意識も異なるでしょうし、
- 働き方改革
- 健康経営
などの世間の動きもあるし、必ずしも「ズブズブの不健康な食生活」というわけではないと思われますが、それでも食育活動の対象としては「巨大な市場」であることは間違いないでしょう。
近年は
- 良い仕事をしたければ食事に気を使うべきだ
- 出世する人ほど食生活がちゃんとしている
という主張のもと、サラリーマン市場を対象に食育活動を展開する動きも始まっています。
こうした動きには大きく分けて4つの活動テーマが考えられます。
2-1.体調回復
まず1つは「体調回復」というテーマ。
サラリーマンは
- 朝食を抜いたり
- 麺類を食べることが多かったり
- 飲酒が多かったり
- 遅い時間の食事が多かったり
なので体調が良くないまま仕事をしている。
そこで、食事を改めることで体調を整え、結果的に仕事の能率を上げよう、という主旨の食育活動です。
2-2.ブレインフード
また1つは「ブレインフード」というテーマ。
脳に良いとされる食材(ブレインフード)を計画的に食べ、
- 忙しいときには集中力を上げたり気分を高めたり
- そうでないときにはリラックスしたりよく眠ったりと
食によって上手に脳の働きやメンタルをコントロールしようという主旨の食育活動。
2-3.フーディー
また1つは「フーディー」というテーマ。
アルファベットでは foodie と書き、食に対する関心・意識・知識の高い人を指す言葉です。
接待の場などで
- 食事のマナーが良い
- 店選びのセンスがある
- ワインを上手に選べる
- 食の知識が豊富で会話が楽しい
といったことであれば、その接待はとてもうまくいくし、契約の成功率も上がる。
接待にかぎらず、食に対する関心・意識・知識が高いことで、社内・社外のコミュニケーションが豊かになることが考えられます。
漫画「美味しんぼ」の主人公は「ぐうたら社員」とされていますが実はハイレベルな「フーディー」であり、その「フーディーさ」により、さまざまな人脈を築くことができ、結果的に「ぐうたら社員でありながら勤める会社に大いに貢献している」と言えます。
食は万人共通の関心ごとであるため、食に詳しいことはビジネスの場でも大いに役に立つのです。
2-4.料理の活用
最後の1つは「料理の活用」というテーマ。
自分で料理をする人は料理を通じて「段取り上手」になれる。
仕事も料理も「段取り」が大事。
だから、仕事のできる人になりたければ日常的に料理をする習慣をつけよう、という主旨の食育活動です。
いずれのテーマも「仕事で成果を上げたい」というビジネスパーソン(サラリーマン)の願いを食育活動とリンクさせています。
3.まとめ
「食育ブーム」のころは、猫も杓子も「食育=子どもの栄養教育」という固定観念にとらわれていたため、過当競争を呈していました。
これからの食育は「食育=子どもの栄養教育」という固定観念から離れ、新しい市場に進んでいくべきです。
たとえば「ビジネスマン」という市場があり、
- 食によるビジネスマンの体調回復
- ビジネスマンのためのブレインフード
- フーディ(食に詳しくなり、社内・社外のコミュニケーションに活かす)
- 料理の活用(料理の習慣をつけることで段取り力を上げる)
といった食育活動を提案することができます。
- 検定試験を受けるのにメールアドレスの登録などは必要ありません。
- 合格者全員に進呈:「食育活動スタートアップガイド(PDF)」