
英語検定、漢字検定など、世の中にはさまざまな「検定」が存在しています。
硬いものもあれば柔らかいものもあり、難しいものもあれば気軽なものもあります。
今回、解説したいのは
「検定を主催する」
ことについてです。
検定は「受ける」ものだとばかり思い込んでいませんか?
それは受け身の考え方です。
発想を変え、検定を「実施する=主催者になる」ことも、じつは可能です。
「実施する=主催者になる」立場で、検定というものを見直してみましょう。
|
<目次>
|
1.検定とは
検定とは、試験を行って合否や等級などを認定することです。
いわゆる資格講座の場合は「講座」と「試験」がセットになっていることが多いのに対し、検定の場合は「試験のみ」の構成となっています。
検定に合格するために「講座」が開かれることもありますが、そのような講座は、検定試験とは異なる主催者によって実施されるのが普通です。
この構造は
- 大学入試:大学が「試験」のみを実施する
- 塾や予備校:入試に合格するために「講座」を実施する
とよく似ています。
2.食や食育に関する検定例
世の中にはさまざまな「検定」が存在していますが、食や食育に関する検定もいろいろあります。
硬いものもあれば柔らかいものもあり、難しいものもあれば気軽なものもあります。
いくつか、比較的「本格的なもの」の事例を挙げておきます。
2-1.北海道フードマイスター検定
2-2.日本さかな検定(ととけん)
2-3.日本酒検定
2-4.農業検定
2-5.食の検定
2-6.家庭料理検定
3.食育総研が実施する検定例
食育総研では、食育活動のレベルアップにつながるオンライン検定試験の開発を進めています。
3-1.食育イノベーター検定
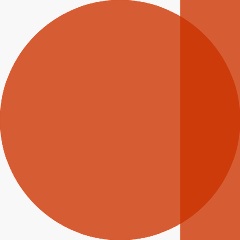
「食育イノベーター」とは、「時代のニーズをとらえた食育活動を生み出す人」。
いま人々が関心を寄せていることを入口にして、自由な発想の食育をどんどん生み出すクリエイティブな思考と、ほんとうに社会に浸透させるべき食育に関する本質的な知識を併せ持つ人材。
そんな資質をもつ人が「食育イノベーター」です。
3-2.ブレインフード検定

ブレインフードとは
「脳の働きを良くする力のある食べもの」
のこと。
- 記憶力
- 集中力
- 精神状態
に良い影響を与える食事のことを指します。
ブレインフード検定は、ブレインフードの知識を、人生100年時代の食の常識として社会に定着させるための検定試験です。
3-3.プラントベース検定

プラントベース検定は、日本で唯一の「プラントベース」をテーマにした検定です。
世界では浸透が進んでいる「プラントベースフード(植物性の食)」ですが、日本ではまだ言葉すら聞いたことがない人がほとんどという状況です。
そこで一人でも多くのプラントベースの理解者やプラントベースを楽しめる人を増やすために、プラントベース検定をスタートしました。
監修は、日本初のプラントベースの啓蒙を行う『植物性料理研究家協会』に行ってもらっています。
3-4.ファイトケミカル検定

ファイトケミカルとは、野菜や果物などの植物性の農産物が持つ「機能性成分」で、いわゆる5大栄養素に分類されないものを指します。
ファイトケミカルは、植物が自分自身を紫外線などから守るために体内で作りだしているものですが、人間の健康にも役立つものが多いと考えられています。
ファイトケミカル検定は、ファイトケミカルをはじめとした、農産物(野菜、果物、キノコ類、豆類、穀類などの植物性の食べもの)の持つさまざまな「機能性」の知識を、広く社会に伝えるための検定です。
- 生活者はこの知識を学ぶことで、食卓がさらに豊かになります。
- 生産者はこの知識を学ぶことで、作っている作物の新しい魅力(とくに栄養価値)を発見することができます。
3-5.食育フードテック検定

「フードテック」は
- Food(食)
- Technology(テクノロジー)の Tech
を組合せてできた造語。
「科学の知識や技術を食に応用する」という意味になります。
近い将来、人々の食生活を激変させるであろうフードテック。
フードテックは食育のありかたにも大きな影響を与えると思われます。
4.検定のビジネスモデル
テクノロジーの発達や人々の嗜好の変化などにより、「検定」のビジネスモデルにも変化が見られます。
4-1.旧型のビジネスモデル
旧型の「検定」の特徴は以下です。
- 受験料が有料=受験料がキャッシュポイントとなっている
- 試験会場が用意され、紙ベースで試験が行われる
4-2.新型のビジネスモデル
新型の「検定」の特徴は以下です。
- 受験料は無料=試験とは別のところにキャッシュポイントが用意されている
- ネット上で試験が実施される
5.検定を「持つ」
5-1.「受ける」から「主催する」へ
これまでは、
- 試験会場を用意する
- 試験問題を印刷する
- 受験者を集める
という手間と費用がかかったため、個人が検定試験を主催することはあまり現実的ではありませんでした。
しかしテクノロジーの進化により、ネット上で試験を実施することが可能となったため、個人でも検定試験を作成し、ネット上にそれをリリースすることができるようになっています。
この傾向はますます進むと考えられます。
これまでの検定は「受ける」だけのものでしたが、これからの検定は「主催する」こともできる。
言い換えれば、
- 検定を「持つ」
- 検定のオーナーになる
こともできるというわけです。
5-2.「持つ」ことの意義
個人がオリジナルの検定試験を「持つ」意義は、以下です。
- 検定試験は自分の食育活動に興味を持ってもらう有力なツールとなる
- 検定試験をリリースしていることじたいが、自分の食育活動の信頼性を高める
- 名刺に、オリジナル検定を「持っている」ことを表示することができる
6.まとめ
個人が自分のオリジナルの「検定」を持つことは、かつては考えられませんでした。
しかしテクノロジーの発達により、それが可能となってきています。
「検定」を食育活動のツールとして活用してみませんか?
(あわせて読む)イノベーション型検定 x 食育



